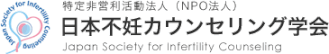せんねん灸セルフケアサポーター・日本不妊カウンセリング学会会員
冷えたり、のぼせたりする
現代医学的な考え方

冷えとは、背中や腰、手足などの一部分が特に冷たく感じる訴えを指し、のぼせとは、顔がほてる、頭がのぼせるなどの自覚症状を指します。
いずれの症状も、原因疾患があって起こってくる場合とそうでない場合とがあります。
冷えの原因疾患には貧血症のほか、手足の動脈系血管障害があり、のぼせを起こす原因疾患には、多血症などがあります。
原因のはっきりしない冷えやのぼせは、婦人に多くみられ、更年期障害を伴う自律神経系の乱れに由来しています。このほか、心因性のものもあります。
注意を要する冷え、のぼせ
【冷え】
動悸、息切れ、貧血などがみられるもの(貧血症)や、手足の先端の傷が治りにくいなどの症状があるもの(四肢血管障害の重症例)は、一度医療機関で診てもらってください。
【のぼせ】
動悸、息切れ、ピンク色の痰や尿が出にくいなどの症状を伴うもの(多血症の重症例)や、胸や手に静脈の怒張が認められるもの(上大静脈症候群)、のぼせ以外に腹痛、下痢、喘息様症状などを伴うもの(カルチノイド症候群)は、一度医療機関で診てもらってください。
鍼灸の適応となる冷え、のぼせ
更年期障害や、レイノー病、バージャー病の軽症例が適応となります。
更年期障害とは、閉経期の内分泌異常に伴う自律神経の機能異常により局所の血管異常が乱れ、局所の血流が多くなったり、妨げられたりして症状を起こします。
レイノー病、バージャー病は、手足の動脈系の血管障害です。
東洋医学的な考え方
I.のぼせ
のぼせは女性に多くみられ、顔がほてる、頭がのぼせる、全身がほてる、足がほてるなどを訴えます。
また、下半身の冷えと上半身ののぼせを同時に伴っている場合もあり、これは、「上熱下寒(じょうねつげかん)」と言われています。
多くの場合、東洋医学的に考える心臓の熱が下降できず、東洋医学的に考える腎臓の水が上昇できない状態になっています。
そのため、上半身の火を消すことができず、かつ下半身の水を温めることができないことが同時に起き、足元は冷えているのに、頭がのぼせている、という症状が出現します。
II.冷え
身体の特定部分だけが特に冷たく感じるものを、冷え症と言い、女性に多くみられます。
内因としては陽虚(ようきょ)があり、外因としては、冷房や寒湿などがあります。
陽虚とは、身体を温める作用(温煦作用)が低下することを言います。
陽虚になると、血行が悪くなり瘀血(おけつ=血液が滞る状態)を形成し、さらに血行を悪るくなり、冷えもさらに生じるようになります。
東洋医学的な冷え、のぼせの原因
生まれつき、東洋医学的に考える腎臓の働きが弱かったり、慢性病や出産などによって、東洋医学的に考える腎臓の働きが弱まったりすると、火と水のバランスが崩れ、上熱下寒があらわれるといわれています。
施術方針
東洋医学的に考える腎臓と心臓の交通がうまく通るようにし、陰陽のバランスを回復させます。
東洋医学的に考える腎臓は、年齢とともに機能が低下していきますので、自宅でのセルフケアを心がけてください。
営業日カレンダー
6月のお灸教室は、第3日曜日に行います。完全予約制のため、お早めにご予約ください。
Copyright © 2012 山本鍼灸院 All Rights Reserved.