せんねん灸セルフケアサポーター・日本不妊カウンセリング学会会員
東洋医学の「大腸」の働き
東洋医学の「大腸」の生理作用と病理作用

現代医学の大腸の働きは、小腸から送られてきた液状の内容物から水分を吸収し、糞便にします。この糞便をがまんするため溜めたり、肛門からの排便が主な働きになります。
東洋医学の大腸の働きは、ほぼ同じで、食べ物のカスを外に出す働きがあります。東洋医学の言葉を用いると、
「糟粕の伝導を主る(そうはくのでんどうをつかさどる)」
となります。
この大腸に異常をきたすと、排便異常を引き起こします。
具体的には、下痢や便秘になります。
病理変化も、現代医学と東洋医学で、ほとんど差が無いことがわかります。
「大腸」に属するツボは20個

大腸は、東洋医学の「陰」と「陽」に分けると、「陽」に属します。
さらに「陽」を分けると、「太陽」、「少陽」、「陽明」の3つになります。
大腸は、手の「陽明」に属していて、20個のツボを有します。
難しい話しになってしまいましたが、「大腸」の性質を持ったツボが20個あり、そのツボもそれぞれ特性を持っています。
今回は、ツボの特性の前に、ツボの名前を列挙します。
- 商陽(しょうよう)
- 二間(じかん)
- 三間(さんかん)
- 合谷(ごうこく)
- 陽渓(ようけい)
- 偏歴(へんれき)
- 温溜(おんる)
- 下廉(げれん)
- 上廉(じょうれん)
- 手三里(てさんり)
- 曲池(きょくち)
- 肘髎(ちゅうりょう)
- 手五里(てごり)
- 臂臑(ひじゅ)
- 肩髃(けんぐう)
- 巨骨(ここつ)
- 天鼎(てんてい)
- 扶突(ふとつ)
- 禾髎(かりょう)
- 迎香(げいこう)
大腸に属するツボはそれほど多くありませんが、様々なツボの特性があります。


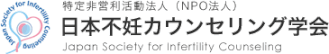

コメントをお書きください